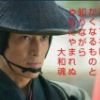-
[9]
歴史は現代の生き物
杉さんぼく
京都の町はどの時代をとっても、その歴史には趣がある。
わけても、誰かが主役になり誰かが脇役になり事件が起こって、闇に蠢く幕末維新の京舞台は、心ときめく面白さがあり、ドラマチックですらあるのは否めない。
例えば、「このたび、六月五日夜、洛陽動乱の一条」と、新選組局長近藤勇が書いた元治元年の、三条旅宿池田屋 ・・・・ >> 続き歴史は現代の生き物 杉さんぼく 2015/07/15 18:33-
[79]
石高の単純な計算を記せば、現在、仮にコシヒカリなりを5kg2880円としたら、1kg576円です。
1升は1.4kgですから、これに576円を掛けると806円40銭になります。
806円をわかりやすく800円として、100升は10斗で1石、1両、銀60匁ですから、100升掛ける800円となり80000円(8万円)になる訳です。
銀60匁=銭4000文が8万 ・・・・ >> 続き石高でいくら 杉さんぼく 2015/07/31 17:59 -
[90]
そうですね、ここに知られざる歴史は現代の遺跡を紹介します。
大阪石橋の阪大総合博物館裏手の待兼山に、忘れ去られた駐蹕碑(天皇行幸啓)が建っています。
今上陛下行幸記念碑です。
そう言えば、昨年(2014)の6月25日に、この阪大総合博物館の緒方洪庵資料をご覧に、天皇皇后両陛下が来られました。
昭和4年に昭和天皇は大阪に来ら ・・・・ >> 続き歴史は現代、現代は歴史の忘れられた遺跡 奥津希多世ママ 2015/08/11 12:25-
[93]
西郷頼母の家族自刃で、西郷家口伝に、介錯は薩摩の中島信行(実は土佐だが)と通説にありますが、当時、中島作太郎信行は会津には行っていない、それは中島茶太郎の間違いだろう、と土佐の史家平尾道雄が論を唱えました。
ところが、、西郷家口伝に薩摩とある中島信行、実はこれは薩摩の「川島信行」が正しかったんですね。
活字、誤写で「川」「中」にデフォルメ喧伝された訳です。
この川島信 ・・・・ >> 続き歴史語り 杉さんぼく 2015/08/14 05:55-
[173]
弱腰の日本を見くびって韓国が実効支配する竹島、竹が生えるから竹島でもありませんが、語源的には、タキ・タケなどは、急峻な地形を意味するそうで、ようは竹というのは当て字なんだとか。
どうやら昔、日本では鬱陵島を竹島と呼び、現在の竹島は松島と呼んでいたらしく、なぜ松島のままではなかったのかはわかりません。
この、竹島/独島問題の一因は、こんにち韓国領として確定 ・・・・ >> 続き歴史語り・竹島 杉さんぼく 2015/10/22 17:49-
[174]
日本について知識のあったシーボルトは、朝鮮半島と日本の間に竹島と松島という2つの島があって、日本に近い島が「松島」、朝鮮半島に近い島が「竹島」であることを知っており、その著『日本』において、当時の欧米の地図に表記されていた朝鮮半島寄りの「アルゴノート島」に「竹島」、もう一方の「ダジュレー島」に「松島」の名を当てたのです(大熊良一著『竹島史稿』原書房1968)。
現在、竹島=独 ・・・・ >> 続き歴史語り・続・竹島 杉さんぼく 2015/10/22 17:51
-
[174]
日本について知識のあったシーボルトは、朝鮮半島と日本の間に竹島と松島という2つの島があって、日本に近い島が「松島」、朝鮮半島に近い島が「竹島」であることを知っており、その著『日本』において、当時の欧米の地図に表記されていた朝鮮半島寄りの「アルゴノート島」に「竹島」、もう一方の「ダジュレー島」に「松島」の名を当てたのです(大熊良一著『竹島史稿』原書房1968)。
-
[173]
弱腰の日本を見くびって韓国が実効支配する竹島、竹が生えるから竹島でもありませんが、語源的には、タキ・タケなどは、急峻な地形を意味するそうで、ようは竹というのは当て字なんだとか。
-
[200]
西宮神社吉井良隆宮司から、今は第554代良昭宮司になってるんですね。
その傍系の吉井宮司と言えば貞俊権宮司が、伊勢本街道で馴染みが深いんですが、なぜか、「良」がつくのにこの権宮司さんは貞俊と言うお名前で、残念ながら故人になられてしまいました。
吉井一族は皆さん健筆家です。
西宮史話の良隆宮司以前に、14歳から国書神典を父良幹に受けた影響からか、 ・・・・ >> 続き歴史は現代、西宮宮司さん 奥津希多世ママ 2015/11/27 05:11
-
[93]
西郷頼母の家族自刃で、西郷家口伝に、介錯は薩摩の中島信行(実は土佐だが)と通説にありますが、当時、中島作太郎信行は会津には行っていない、それは中島茶太郎の間違いだろう、と土佐の史家平尾道雄が論を唱えました。
-
[79]
石高の単純な計算を記せば、現在、仮にコシヒカリなりを5kg2880円としたら、1kg576円です。
[ 編集 ][ 返信 ]歴史は現代の生き物
杉さんぼく
歴史は現代の生き物
杉さんぼく
京都の町はどの時代をとっても、その歴史には趣がある。
わけても、誰かが主役になり誰かが脇役になり事件が起こって、闇に蠢く幕末維新の京舞台は、心ときめく面白さがあり、ドラマチックですらあるのは否めない。
例えば、「このたび、六月五日夜、洛陽動乱の一条」と、新選組局長近藤勇が書いた元治元年の、三条旅宿池田屋御用改めはあまりにも有名である。
しかし、今でもよく判らない通説がありそれを突き崩すのは難しい。
最近でこそ、偶発的な事件であった、とは言えるにもせよ、映画、ドラマ、小説等の世界はそれでは納得しない。
試みに、当時四条大宮に住む質屋渡世鍵屋長治郎町日記を繰ると
「六月五日晴天、昨夜ヨリ三条河原丁二条迄之間ニ而大混雑、浮浪之者忍入居リ聞ニ付、不意ニ押寄四五斗切殺、拾壱人生捕。…」(高木在中日記)とあり、二条から三条辺りの旅宿街で御用改めがあった事を記している。
いずれにしても、日本史上さしたる事ではないこうした事件を、小説家などは資史料を元に嘘と虚構の世界を創り出してゆく。
では、燃えよ剣、新選組血風録を世に送り出した司馬遼太郎氏の弁はどうだろう。
「…史料自体は何も真実を語らない。そこに盛られているのはファクトにすぎず、このファクトをできるだけ多く集めないと真実が出てこない。しかし、ファクトにとどまっていると向こうにいけないのでそのためにもファクトは親切に見なければならない」(手堀り日本史-1972年)
今一人、西郷隆盛を描いたら、その右に出るものはいない薩摩の作家、海音字潮五郎氏の謂いはもっと痛烈である。
「…うまい小説家というのは、みんなうそつきなんですね、小説に書かれている心理、人間、これは実際とは別もんなんであります。作者の心を通じてこしらえあげられたものです。実在的なものに見せかけているのです。現実の社会に放り出してごらんなさい、直ちに滅亡ですよ」(さむらいの本懐-1975年)
俗に司馬史観と言われるように、事実を史実に変え、嘘と虚構を超越した事実への挑戦産物が、それぞれの史観たる史観のそれがゆえんなのかも知れない。
続く→
2015/07/15 Wed 18:33 [No.9]
[ 編集 ][ 返信 ]石高でいくら
杉さんぼく
石高の単純な計算を記せば、現在、仮にコシヒカリなりを5kg2880円としたら、1kg576円です。
1升は1.4kgですから、これに576円を掛けると806円40銭になります。
806円をわかりやすく800円として、100升は10斗で1石、1両、銀60匁ですから、100升掛ける800円となり80000円(8万円)になる訳です。
銀60匁=銭4000文が8万円で、一文は20円、当時の28そばが320円で食べられたんですね。
そして、俗に二束三文と言われるのは、わらじが二束で60円だったと云うことでした。
小判壱両は二分銀2枚、一分銀は4枚 二朱銀は8枚 一朱銀が16枚で金壱両となります
そして江戸は金使い 上方は銀使いでした。
この通貨は 金壱両に銀60匁が相場です
一円が10枚で10円玉になるようなものです
歴史勉強する基本に 新旧暦や貨幣制度も知る必要はありますね
ちなみに、千両箱は8000万円、重い筈のなにものでもありません。
1石=銀60匁=16朱=4分(歩)=1両
1石=10斗=100升=1升=10合
1升800円(100升8万円)
余談ですが、長州藩が武器弾薬を購入する6万両を山口から下関へ現送するのに、一頭の馬に千両箱五つをつけた12頭に予備馬を加え14頭行列で運んだと言います。
2015/07/31 Fri 17:59 [No.79]
[ 編集 ][ 返信 ]歴史は現代、現代は歴史の忘れられた遺跡
奥津希多世ママ
そうですね、ここに知られざる歴史は現代の遺跡を紹介します。
大阪石橋の阪大総合博物館裏手の待兼山に、忘れ去られた駐蹕碑(天皇行幸啓)が建っています。
今上陛下行幸記念碑です。
そう言えば、昨年(2014)の6月25日に、この阪大総合博物館の緒方洪庵資料をご覧に、天皇皇后両陛下が来られました。
昭和4年に昭和天皇は大阪に来られていますが、それ以前、荒れ放題の駐蹕跡碑とある裏面には、今上陛下、大正5年の刻字があり、再度の来阪でした。
この駐蹕碑(天皇行幸啓)について、昨年、天皇両陛下を案内されて説明されたかどうか…。
一方、その荒廃碑がある待兼山には、何かと権力闘争で宣(かまびす)しい朝鮮問題の重い歴史がありました。
1950年6月25日、北朝鮮が38度線を越えて南下した事から、国連軍、中国軍が参戦、ジェット機空中戦が初めて行われた朝鮮戦争が勃発、ソ連提案で1953年7月27日休戦協定調印し、朝鮮半島分断で今に至っています。
この戦争に絡んださなか、待兼山から1952年6月24日〜25日に事件が起こりました。
いわゆる吹田枚方事件です。
朝鮮戦争前夜祭として、待兼山に竹槍、火炎ビンを手にした朝鮮系学生1000人以上余りが集結、駐留軍宿舎のあった伊丹や輸送列車のある吹田操車場を襲撃目標としました。
ところが、厳戒警備のために警官隊と衝突しながらその拳銃を奪い、右翼大物笹川良一宅や駐留軍准将宅に火炎ビンを投げ、吹田駅停車中の車両に雪崩れ込み、拳銃、火炎ビンで抵抗、そして別同隊の学生数人は、枚方の旧陸軍工廠に爆弾を仕掛けたりして、検挙者総数は100人あまり以上が出ました。
日本が特需景気に湧いて戦後経済の弾みになった朝鮮戦争でしたが、これに呼応して、こうした事件は全国で起こったとされています。
例えば京都三条の島津製作所では、破防法反対などでパトカーが火炎ビンで襲われたり、警官隊に重軽傷を負わせています。
さて、何の因果が昨年の天皇両陛下来阪が6月25日でした。
まさにその日、荒れた駐蹕碑のある待兼山に、集結したことから起こった事件が6月25日、偶然にしても大学側はご存知だったのかどうか…。
いずれにしても、両陛下はその駐蹕碑まで案内はされていなかったでしょう。
案内されたなら、その道、石段もきれいに整備されているのではないでしょうか。
2015/08/11 Tue 12:25 [No.90]
[ 編集 ][ 返信 ]歴史語り
杉さんぼく
西郷頼母の家族自刃で、西郷家口伝に、介錯は薩摩の中島信行(実は土佐だが)と通説にありますが、当時、中島作太郎信行は会津には行っていない、それは中島茶太郎の間違いだろう、と土佐の史家平尾道雄が論を唱えました。
ところが、、西郷家口伝に薩摩とある中島信行、実はこれは薩摩の「川島信行」が正しかったんですね。
活字、誤写で「川」「中」にデフォルメ喧伝された訳です。
この川島信行の談が、絵本西郷一代記かに記載がありますから、間違いないでしょう。
中島作太郎、茶太郎がもやもやしていましたから、これで一件落着です。
(参考資料は堀田節夫氏による)
2015/08/14 Fri 05:55 [No.93]
[ 編集 ][ 返信 ]歴史語り・竹島
杉さんぼく
弱腰の日本を見くびって韓国が実効支配する竹島、竹が生えるから竹島でもありませんが、語源的には、タキ・タケなどは、急峻な地形を意味するそうで、ようは竹というのは当て字なんだとか。
どうやら昔、日本では鬱陵島を竹島と呼び、現在の竹島は松島と呼んでいたらしく、なぜ松島のままではなかったのかはわかりません。
この、竹島/独島問題の一因は、こんにち韓国領として確定している鬱陵島との取り違えからもたらされたようです。
確かに江戸時代、日本人は竹島/独島を「松島」、鬱陵島を「竹島」と呼んでいました。
松陰が訪ねる文献資料の旅に、長久保赤水がいました。
その著す「日本輿地路程全図」(1775年)には、はっきり松島・竹島の名称が付され、大西教保の『隠岐古記集』(1823)には、「『松島』は小さな生木なき岩島、『竹島』は竹木繁茂した大島」(川上健三著『竹島の歴史地理学的研究』古今書院1996)とあり、竹島/独島と鬱陵島に対して、鬱陵島=竹島とする呼称が江戸時代には行われていたようなのです。
「竹島」の島名が逆転し、現在の島に与えられるようになったのは、ヨーロッパ人が鬱陵島を「発見」し、また長崎出島オランダ館の医師シーボルトによる誤った島名の混乱に端を発すると言います。
1787年、フランスの航海者で、こんにち宗谷海峡の国際名称に名を残すラ・ペルーズは、航海の途中で鬱陵島を見つけ、これを「ダジュレー島」と命名、ついで、1789年イギリス探検家ジェームス・コルネットがこの鬱陵島を見つけ、「アルゴノート島」と命名しました。
実は、この2島は同じ島でありながら、報告された際の位置が異るため、欧米の地図上には、日本海にダジュレー島とアルゴノート島の2島が存在する表記になってしまいました。
2015/10/22 Thu 17:49 [No.173]
[ 編集 ][ 返信 ]歴史語り・続・竹島
杉さんぼく
日本について知識のあったシーボルトは、朝鮮半島と日本の間に竹島と松島という2つの島があって、日本に近い島が「松島」、朝鮮半島に近い島が「竹島」であることを知っており、その著『日本』において、当時の欧米の地図に表記されていた朝鮮半島寄りの「アルゴノート島」に「竹島」、もう一方の「ダジュレー島」に「松島」の名を当てたのです(大熊良一著『竹島史稿』原書房1968)。
現在、竹島=独島と呼ばれる島は、フランスの捕鯨船リアンクール号によって、1849年「発見」され、リアンクール島と命名されています。
或いは、ハイネの「日本近海図」に見られるように、ヨーロッパの地図には、西からアルゴノート島、ダジュレー島、リアンクール島と、3つの島が描かれる地図も出現しました。
ところが、1854年にロシアの軍艦パルラダ号が鬱陵島の正確な位置を調査したところ、アルゴノート島の経緯度の測度が不完全であるとわかり、このため、アルゴノート島は、欧米の地図において、存在が不確実である事の点線囲みで表示されるようになり、やがては全く表示されなくなって、シーボルトが与えた「竹島」の名とともに地図から姿を消してしまっています。
これらの島を開拓しよう、と龍馬(海援隊)が計画していた説が最近浮上、龍馬亡き後は岩崎弥太郎が同じ様に開拓計画を立てていた話もあります。
しかし龍馬のめざした竹島は、現在問題になっている竹島ではなく、鬱陵島の事らしい。
その鬱陵島については、幕府は元禄9年(1696)の時点で渡海禁止令を出しています。
朝鮮領と認めていたからです。ただし、これは鳥取藩にだけ通知されていただけで、その後も鬱陵島に渡る者が続出したので、天保8年(1837)に全国的に二回目の渡海禁止令を出しました。
どうやら龍馬は、鬱陵島が朝鮮領と認定されているのを知らなかった様で、従って龍馬の竹島開拓計画は、鬱陵島に渡ろうとした想いだけで、例のいろは丸の沈没で出鼻をくじかれたまま挫折しました。
彼が殺されずに生きていて、開拓計画をすすめていれば当然領土問題に突き当たったかも知れません。
2015/10/22 Thu 17:51 [No.174]
[ 編集 ][ 返信 ]歴史語り・続々・竹島
杉さんぼく
幕府の鳥取藩への、元禄9年1月28日(正月廿八日)[西暦1696年3月1日]付老中の連署布達
「向後 竹島へ渡航之儀 制禁 可申付旨 被仰出之候間」因幡鳥取藩藩主池田綱清(松平伯耆守)宛で、竹島(=現鬱陵島)渡航禁止を通告しています。
幕府の見解は、竹島(=現鬱陵島)には、我が国の命により日本人の竹島(=鬱陵島)への出漁を禁じたことを知らせました。
龍馬が知らなかった布達ですが、さすがに情報通だったのが桂小五郎です。
安政5年7月11日付けの桂小五郎宛て書状がそれを記している。
「竹島・大坂島・松島合せて世に是れを竹島と云ひ、二十五里に流れ居り候。竹島計り十八里之あり、三島とも人家之れなく候。大坂島に大神宮の小祀之れあり、出雲地より海路百二十里計り。産物蛇魚類、良材多く之れあり、開墾致し候上は良田美地も出来申すべし。此の島蝦夷の例を以て開墾仰せ付けられば、下より願ひ出で航海仕り候もの之れあるべく候。」
松浦武四郎の「竹島雑誌」が竹島の周回を16里、出雲の島根半島の雲津から隠岐経由竹島までが約120里としていること等から考察すると、竹島から松島まで25里は同じ鬱陵島を竹島(アルゴノート島)と松島(ダジュレー島)とした1840年以降のシーボルトの「日本図」に合致しています。
松陰が「万国地図」、すなわち世界地図から竹島を確認し、最近まで元禄竹島一件の事は知らなかった、と語っている事からも島も現在の竹島でないのが判ります。
時に、大坂島を大坂浦とされるが、大坂浦に近い島の意味で、竹島とも呼ばれていた竹嶼の事かも知れません。
2015/10/22 Thu 19:07 [No.175]
[ 編集 ][ 返信 ]歴史語り・続々々・竹島
杉さんぼく
吉田松陰が処刑された翌年の万延元(1860)年7月2日に、桂小五郎と村田蔵六が連名で幕府に提出した「竹島開拓建言書草案」は、松下村塾の竹島開拓論の集大成といって良いかもわかりません。
まず開拓の必要について。
竹島は長門国萩より東北の海上約50里にあって、朝鮮から竹島までも約50里なのでほぼ等間隔にある事。
最近外国船が竹島周辺に出現するようになってきており、植民でもして国防を考える必要がある事。
北前船が下関へ往復する時暴風暴波の折には竹島に碇泊して天気の回復を待っている事。
すでに島には日本人が建てた人家が5、6軒はあると聞いている事。
かって朝鮮国へお渡しになったという風聞もあるが、朝鮮人の渡海は皆無である事。
世界地図を見ると日本と同じ色に着色され、島名も「タケエイ・ララド」と記され、日本の属島と認識されているのが明白である事。
万一この島が外国の手に落ち植民でもされた時は、日本や直近にある長州にとって多大の禍になる事。
と、これらが急務であり必至であるのを列挙しています。
この竹島開拓建言書草案は、幕府の閣老久世広周(くぜひろちか)に提出されましたが、藩主建白書でないという理由で却下されています。
まさに内憂外患の政治状況でした。
ということで、まずは思うままに…。
2015/10/23 Fri 06:47 [No.176]
[ 編集 ][ 返信 ]歴史は現代、西宮宮司さん
奥津希多世ママ
西宮神社吉井良隆宮司から、今は第554代良昭宮司になってるんですね。
その傍系の吉井宮司と言えば貞俊権宮司が、伊勢本街道で馴染みが深いんですが、なぜか、「良」がつくのにこの権宮司さんは貞俊と言うお名前で、残念ながら故人になられてしまいました。
吉井一族は皆さん健筆家です。
西宮史話の良隆宮司以前に、14歳から国書神典を父良幹に受けた影響からか、その才覚を生かして、幾多の著述を残した吉井良秀に尽きます。
「老父の御神幸に関する記事は後人にとっては誠に有益」と、息、良尚宮司が記すように、その遺稿「樟園余影」(昭和15年)がなかなか良い。
この良秀宮司、年譜によれば
「37歳(明治22年)、信州の国学者飯田武郷の門について、皇典・歌文を研究し始めた」
とあります。
云わずと知れた、飯田武郷は信州下諏訪で斬首された赤報隊相楽総三の首を奪って埋めた、とされる平田国学の雄でした。
意外な繋がりがあるんですね。
だから、歴史は面白い。
2015/11/27 Fri 05:11 [No.200]
[ 編集 ][ 返信 ]西宮神社宮司さん?
杉さんぼく
国書神典の系譜吉井良秀にの遺稿「樟園余影」(昭和15年)が、信州の国学者飯田武郷の門人だったんですか。
確かに、飯田武郷は信州に多くの系譜流布する平田国学の第一人者で、相楽総三の首を奪って埋めた、とされています。
なるほど、なるほど。
2015/11/27 Fri 06:52 [No.201]